職場や学校生活において、円滑な人間関係を築き、より良い成果を生み出すためには、コミュニケーション能力が不可欠です。しかし、一口にコミュニケーション能力と言っても、聞く力から伝える力まで、さまざまなスキルが求められます。
本記事では、コミュニケーション能力を鍛えることの重要性から、社内研修や教育現場、さらには個人でも取り組める具体的なゲームやツールを17種類厳選してご紹介します。ゲームの選び方や効果的な進め方についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

監修者:岩城成弘(いわしろ あきひろ)
スターバックスコーヒーやウォルト・ディズニー・ジャパンでの豊富な実務経験を活かし、日本全国の企業や教育機関などで、ホスピタリティ研修を開催している。特に、ディズニー流の「おもてなし」を基軸にした、企業のブランド価値を高める研修が人気。実践的かつ成果につながる指導が、多くの企業から高い評価を受けている。
コミュニケーションを鍛えることの重要性
コミュニケーションが得意な方は、相手に関心を持ち、相手の話を丁寧に聞く「傾聴力」に優れています。また、自分の考えや情報を分かりやすく相手に伝える能力も高い傾向にあります。一方で、コミュニケーションが苦手な方は、自分の話が中心になりがちで、相手に一方的な印象を与えてしまうことがあります。
コミュニケーションが得意か苦手かによって、学校や職場での人間関係、チームでの活動のしやすさ、勉強や仕事の効率、そして自分自身の成長度合いまで大きく変わることがあります。円滑なコミュニケーションは、誤解やすれ違いを防ぎ、スムーズな意思疎通を可能にするため、良好な関係を築く上で非常に重要です。
意識的にコミュニケーション能力を鍛えることは、組織にとっても個人にとっても非常に重要です。
社会人向けコミュニケーションゲーム3選
社会人を対象としたコミュニケーションゲームは、チームビルディング、リーダーシップの発揮、交渉力の向上など、実務に直結するスキルの習得を目的としています。対象者の年齢や役職、置かれている状況によって最適なゲームが異なるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ゲーム1:コンセンサスゲーム
内容:ある特定の状況下で、限られたアイテムの中から、生き残るために必要なものの優先順位を個人で考えます。その後チームで意見をまとめ、最終的な結論を導き出すゲームです。
期待できる効果:論理的思考力、傾聴力、説得力、協調性の向上が期待できます。
注意点:ファシリテーターは、議論が停滞しないよう適度に介入し、参加者が発言しやすい雰囲気を作りましょう。また、制限時間内に結論を出すよう意識させることも重要です。
ゲーム2:ペーパータワー
内容:限られた枚数の紙を使って、制限時間内にできるだけ高いタワーを作るゲームです。
期待できる効果:チームワーク、役割分担、創造力、問題解決能力に役立ちます。
注意点:作戦タイムと作業タイムを明確に区切り、効率的な進め方を意識させると良いでしょう。また、タワーが倒れたり、紙で手を切ったりしないよう、安全への配慮も必要です。
ゲーム3:他己紹介ゲーム
内容:参加者同士がペアになりお互いにインタビューを行います。その後、インタビューで得た情報をもとに、ペアの相手を他のメンバーに向けて紹介するというゲームです。
期待できる効果:傾聴力、質問力、要約力、プレゼンテーション能力の向上、相互理解を深める効果があります。
注意点:インタビュー時間を十分に確保する必要があります。また、紹介する内容は、プライバシーに配慮し、相手が不快に思わない範囲で行うよう事前にアナウンスしましょう。
子ども・教育現場向けコミュニケーションゲーム3選
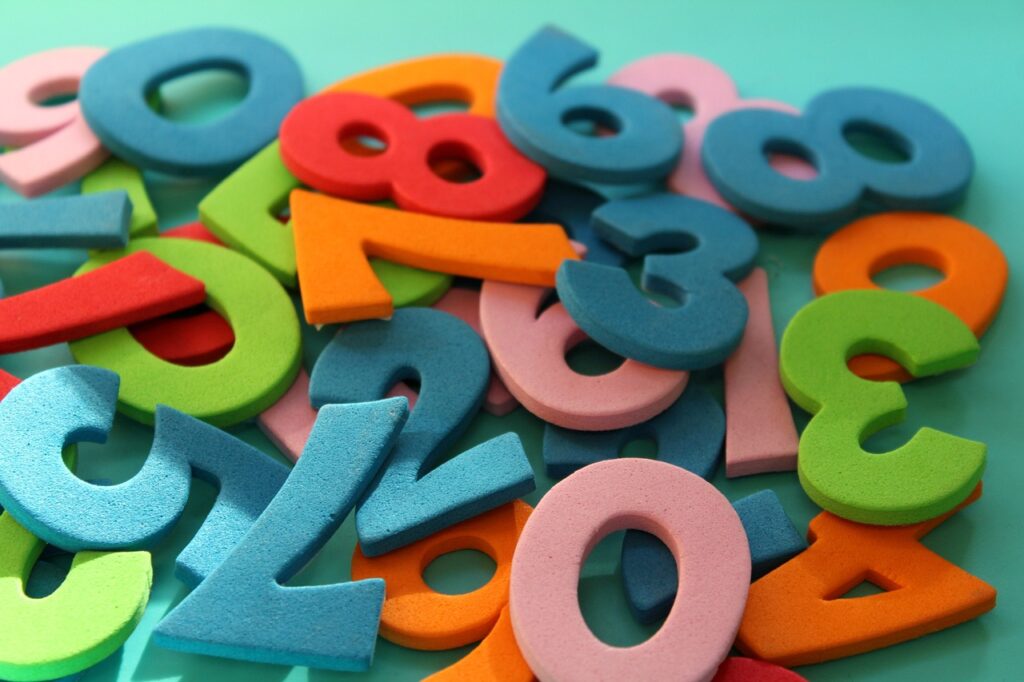
子ども向けのコミュニケーションゲームは、協調性や傾聴力、表現力といった、社会性を育む上で基礎となる能力の育成を目的としています。楽しみながら学べるゲームを選ぶことがポイントです。
ゲーム1:伝言ゲーム
内容:最初の人がお題を次の人に伝え、それを小声で次の人に伝えていきます。最後の人まで正確にお題が伝わったかどうかを確認する、古典的なゲームです。
期待できる効果:傾聴力、集中力、正確に伝える能力の向上が期待できます。
注意点:お題の難易度は参加する子どもの年齢に合わせて調整しましょう。また、伝える声が大きすぎたり、騒がしくなったりしないよう、事前にルールを説明しておくことが大切です。
ゲーム2:ジェスチャーゲーム
内容:出題者がお題を言葉を使わず身振り手振りで表現し、他の人に当ててもらうゲームです。
期待できる効果:表現力、観察力、想像力、非言語コミュニケーション能力を強化します。
注意点:お題の選定を、年齢に合わせて調整しましょう。また、恥ずかしがらずに全員が積極的に参加できるような工夫をしましょう。
ゲーム3:共通点探しゲーム
内容:グループ内でメンバーの共通点をできるだけ多く見つけ出すゲームです。出身地、好きな食べ物、趣味などどんなことでも構いません。
期待できる効果:自己開示の促進、相互理解、親近感の醸成、質問力を身につけるのに効果的です。
注意点:制限時間を設けることで、ゲームに集中しやすくなります。ただし、無理にプライベートな情報を聞き出そうとしないよう、事前の声かけが重要です。
オンラインなど1人向けコミュニケーションツール2選
最近では、オンラインで手軽に取り組めるコミュニケーションツールも充実しています。自分のペースで、場所を選ばずにトレーニングできるのが大きなメリットです。
ツール1:会話シミュレーションアプリ
内容:AIキャラクターなどを相手に、様々なビジネスシーンや日常会話の場面を想定した会話をロールプレイング形式で練習できるアプリケーションです。
期待できる効果:会話の瞬発力、話題提供力、適切な相槌や返答の習得に役立ちます。
ポイント:自分の苦手な場面を選んで練習できる点が魅力です。アプリによっては客観的なフィードバックが得られるものもあり、改善点を見つけやすいでしょう。
ツール2:eラーニング学習
内容:コミュニケーションスキルに関する知識やテクニックを、動画やテキスト教材を通じてオンラインで体系的に学べる学習システムです。
期待できる効果:コミュニケーションの基本原則、傾聴や伝達の具体的な方法論、非言語コミュニケーションの重要性などの理解を深めます。
ポイント:自分の都合の良い時間に、自分のペースで学習を進められるのが大きな利点です。ゲームなどの実践的なトレーニングと組み合わせることで、理論と実践を結びつけ、より効果的にスキルアップを目指せます。
チームの雰囲気を和ませるコミュニケーションゲーム2選
新しいメンバーが加わった際や、会議の冒頭など、少し緊張感のある場面では、まずチームの雰囲気を和ませることが大切です。目的を明確にし、それに合ったゲームを選ぶことで、より効果的なコミュニケーションのきっかけを作ることができます。
ゲーム1:グッドアンドニュー
内容:最近あった「良かったこと(Good)」や「新しい発見(New)」を1人ずつ簡潔に発表していくゲームです。
期待できる効果:アイスブレイク、ポジティブな雰囲気作りに効果的です。
注意点:発表時間に制限を設けると、スムーズに進行できます。発表内容に対して批判的な意見は避け、暖かい雰囲気で聞くことが大切です。
ゲーム2:条件付き自己紹介
内容:通常の自己紹介に、「好きな食べ物と一緒に」「もし自分を動物に例えるなら?とその理由も添えて」といった特定の条件を加えて行うゲームです。
期待できる効果:緊張緩和、相互理解のきっかけ作り、創造性やユーモアを引き出す効果があります。
注意点:設定する条件は、誰もが答えやすく、あまり考え込まずに済むような簡単なものにしましょう。全員が楽しめるテーマ設定を心がけることが重要です。
チームビルディングに活かせるコミュニケーションゲーム2選
チームの結束力を高め、メンバー間の信頼関係を構築するためには、共に目標に向かって協力する体験が効果的です。チームビルディングを目的としたゲームは、楽しみながら一体感を醸成するのに役立ちます。
ゲーム1:自分史ワーク
内容:自分の過去の経験、人生のターニングポイント、大きな喜びや困難だったことなどを時系列で書き出し、それをグループ内で共有し合うワークです。
期待できる効果:相互理解、共感の醸成、信頼関係の構築が期待できます。
注意点:非常にパーソナルな情報を扱うため、プライバシーへの配慮が最も重要です。話したくないことは無理に話させる必要はなく、安心して自己開示できる安全な雰囲気作りを徹底しましょう。
ゲーム2:NASAゲーム(コンセンサスゲームの一種)
内容:「月で遭難した宇宙飛行士」という設定で、限られたアイテムの中から生き残るために必要なものの優先順位を個人とチームで決定するゲームです。
期待できる効果:論理的思考力や多様な意見の尊重、リーダーシップの発揮に役立ちます。
注意点:このゲームには専門家による模範解答が存在するため、ゲーム終了後にチームの解答と比較し、なぜそのような意思決定プロセスになったのかを振り返ることが、学びを深める上で非常に重要です。
論理的思考を養うコミュニケーションゲーム2選
ビジネスシーンにおいては、相手に分かりやすく情報を伝えたり、説得力のある提案をしたりするために、論理的思考力が求められます。ゲームを通じて、楽しみながらこれらの能力を養うことができます。
ゲーム1:図形伝達ゲーム
内容:ひとりがお題となる図形を、言葉だけで他の人に伝えます。他の参加者は、その説明だけを頼りに図形を紙に描いていき、どれだけ正確に再現できるかを競うゲームです。
期待できる効果:正確な伝達能力や傾聴力、質問による確認能力の向上が期待できます。
注意点:伝える側は、お題の図形を相手に見せてはいけません。また、聞く側は、基本的に質問以外の発言を控えるなど、ルールを明確にしておくことで、ゲームの効果が高まります。
ゲーム2:条件プレゼンゲーム
内容:指定された複数のキーワード(例:「リンゴ」「宇宙」「幸せ」など)を全て使い、制限時間内に説得力のあるプレゼンテーションを行うゲームです。
期待できる効果:論理構成力や発想力、表現力、即興での対応能力を磨きましょう。
注意点:キーワードの数や難易度は、参加者のレベルに合わせて調整しましょう。どのような点を評価するのか(論理性、独創性、分かりやすさなど)を事前に共有しておくと、参加者も取り組みやすくなります。
チームビルディング研修について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
コミュニケーション能力を鍛えるゲームの効果的な進め方
コミュニケーション能力を鍛えるゲームを効果的に進めるためには、単にゲームを行うだけでなく、計画から振り返りまでの一連の流れを意識することが重要です。ここでは、具体的な3つのステップで解説します。
ステップ1:事前準備・計画
まず、ゲームの目的を明確にします。次に対象者の人数や年齢層、関係性などを把握し、全員が楽しめ、効果的なゲームを選びます。所要時間や準備物も確認が必要です。進行役(ファシリテーター)を決め、役割を理解してもらい、全体のタイムスケジュールを作成します。
ステップ2:ゲーム実施
開始前に、ゲームの目的とルールを分かりやすく説明し、期待効果も共有して参加意欲を高めます。ファシリテーターは明るい雰囲気を作り、参加者が安心して発言できるよう配慮します。全体の状況を見ながら柔軟に進行し、時間管理を徹底。全員が主体的に参加できるよう促します。
ステップ3:振り返り・フィードバック
ゲーム後には必ず振り返りの時間を設けます。単なる感想だけでなく、具体的な気づきや学びを共有しましょう。何がうまくいき、何が課題だったかを話し合い、得た学びを言語化します。最も重要なのは、ゲームでの経験を実務や日常生活にどう活かすか考え、具体的な行動目標に繋げることです。ファシリテーターは参加者の頑張りを称え、継続を促します。
「面白い研修テーマが思い浮かばない」とお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。
コミュニケーション研修ではゲームをうまく活用しよう
この記事では、コミュニケーション能力を鍛えることの重要性から、具体的なゲームの種類、そして効果的な進め方までを解説してきました。
コミュニケーション能力は、一朝一夕に身につくものではありませんが、ゲームを通して「楽しみながら学ぶ手法」を取り入れることで、より効果的に、そして主体的に鍛えることが可能です。
今回ご紹介したゲームは、あくまで一例です。大切なのは、目的や対象者に合わせて適切なゲームを選び、必ず振り返りを行って次に繋げることです。
コミュニケーション能力は、職場や学校、そして私生活における良好な人間関係の構築に大きく貢献します。ぜひ、積極的にゲームを取り入れ、チームや個人のコミュニケーション能力向上を目指してみてはいかがでしょうか。
もし、より専門的で効果の高いコミュニケーション研修やチームビルディング研修をご検討でしたら、MCSCへご相談ください。経験豊富な講師が、貴社の課題に合わせた最適な研修プログラムをご提供します。

